上埜進研究室
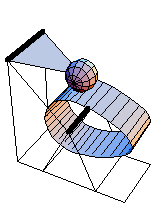
|
上埜進教授の講義(2003年前期) |
|
|
|
|
|
講義の内容・目的 |
|
|
教科書
講義は、『管理会計ー価値創出をめざしてー』の章立てにそくして進める。 |
|
|
講義構成 課題 花王と資生堂の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、製造原価報告書をプリントアウトして次回講義に持参する。 2.1(4/14) 『管理会計ー価値創出をめざしてー』 第2章 財務諸表 また、四回生は『管理会計ー価値創出をめざしてー』のはしがきと目次を読み、管理会計のフレームワークについて自分なりに見解をA4用紙一枚にまとめ、4/28の講義時に提出しなさい。 なお、レポートの書式は35字40行に設定し、最初の行に年月日と題名を、2行目に学籍番号と氏名を、3行目からに本文を書き始める。表紙なし。他人のコピーや本文が30行未満のレポートは未提出扱いとするので要注意。 3. 1(4/21) 『管理会計』第3章 原価計算の基礎例題 『原価計算』 第1章 原価計算総論 3.2(4/21) 『管理会計』第4章 営業量、原価発生額、利益額の関係 任意課題 散布図と回帰分析の例題をエクセルで解き、プリントアウトし次回講義時に持参する。 4.2(4/28) 『管理会計』第5章 意思決定のための関連収益・関連原価 例題 『原価計算』第12章 意思決定会計 第1.3節 任意課題 線形計画の例題をエクセルで解き、プリントアウトし次回講義時に持参する。 5. 1 (5/12) 『管理会計』第6章 投資決定の方法5.2 (5/12) 例題 『原価計算』第12章 意思決定会計 第4 .5.6節 6. 1 (5/19) 『管理会計』第7章 経営戦略の策定6.2 (5/19) 『管理会計』第8章 企業価値の指標とVBM 課題 総合予算のシミュレーション・モデルを理解するために、『原価計算』 第2章および第11章第2節から基礎知識を得ておく。 7. 1(5/26) 『管理会計』第9章 経営計画の策定7.2 (5/26) 『管理会計』 第10章 予算管理 課題 松下電器のアニュアル・レポートからセグメントの事業概況をプリントアウトし、次回講義時に持参しなさい。 8.2(6/2) 例題 『原価計算』 第10章 第7節 9.1( 6/9) 『管理会計』第12章 多国籍企業の利益管理9.2(6/9) 中間試験(教科書持ち込み可)(20点) 四回生で就職活動のため受験できない人は、『管理会計ー価値創出をめざしてー』の第8章「企業価値とVBM」の感想文をA4用紙2枚にまとめ、6/9の講義時に提出しなさい。なお、レポートの書式は35字40行で、一枚目の最初の行に年月日と題名を、2行目に学年、学籍番号、氏名を記載し、3行目から本文を書き始める。表紙なし。他人のコピーは評価対象にしない。 10 .1(6/16) 『管理会計』 第13章 製造プロセスの管理10.2(6/16) 事例 製造業のERP 11 .1 (6/23) 『管理会計』 第14章 標準原価管理11.2 (6/23) 例題 『原価計算』 第7章 事例 病院の原価管理
12.1
(6/30)
『管理会計』 第15章 ABCとサポート部門の原価管理
13.1
(7/7)
『管理会計』第16章 原価企画と原価改善 課題 松下電器のアニュアル・レポート2002から①環境保全活動および②社会貢献活動をプリントアウトし、次回講義時に持参しなさい。 14.1 (7/14) 『管理会計』第17章 ライフ・サイクル・コスティング 14.2 (7/14) 例題 『原価計算』 第13章 原価計算の新領域 第3 .4節
|
|
|
期末試験
なお、三回生の試験問題は、『原価計算の基礎ー理論と計算ー』から、 |
|
|
成績評価
一方通行ではなく、双方向の授業にしたいと思っていますので、協力した人に加点します。
2003年前期の成績分布ですが、三回生は優123名,
良57名,
可66名,
不可8名でした。また、四回生は優19名,
良18名,
可57名,
不可33名でした。不可になった人の多くは、期末試験の一発勝負に挑んでみたものの、総合点で基準点に至らなかった人たちです(03/08/05)。 |
|